スリアラインターナショナルスクールで採用している
イギリスケンブリッジの
カリキュラムでは、英語や英文学のテストのみでなく、数学、科学、歴史、地理に環境問題と、ほとんどの科目で、読解力、文章力が求められます。
授業スタイルは、特に中学生以降からは、先生が一方的に授業をすすめるのではなく、渡された資料等を読み、それについての討論をすることが多くなり、特に、クラス人数の少ないスリアラでは、おのずとそれぞれの発言機会が多くなります。
学内テストといえども、教科書内容を、そのままおぼえればいいだけではなく、テスト問題を読み、それについて1~3ページにも及ぶ論文形式で答える科目もあることから、普段のクラスでの討論の際、どれだけ読みこんで、リサーチをして理解できたか、また、別の意見についても考えてみることから、表現力の向上につながっていきます。
テスト内容、解答のサンプルはこちら。
英語力があがっていくまでの道のり
我が家の話ですが、娘は、小さいころから本を読むのが大好きで、いつでもどこでも本を読んでいるような子です。
この娘は、3歳になるまでは、ほぼ100%日本語で会話をしており、それ以降、ここマレーシアで、英語会話にきりかわりました。
幼稚園、小学校低学年時は、友人のイギリス人、オーストラリア人、ニュージーランド人、南アフリカ人家庭の子供たちと比べると、会話表現力が、ずいぶんと幼稚で、語彙数も明らかに少なかったのです。
これは、英語圏外からの両親をもつ幼馴染の子供たちも同じでした。
ここでの会話表現力というのは、いわれた言葉や物事が理解できないわけではないけれど、ネイティブの人や子供たちが、すっといえる「気の利いたいいまわし」、「生意気な表現」がでてこない。
会話はなりたっているけれど、話がおもしろく進んでいくような言葉のキャッチボールができていないような部分です。(実際には、1日中、走り回って泳ぎ回って遊ぶような子供たちでしたから、気の利いた言葉がでてこなくても、何ら障害はないのですが)
我が家の場合、密着度の高い母親の英語が、日本語訛りが強い(簡単にいうと発音がなってないってことですね)上に、ネイティブに比べ、明らかに語彙数が少ない英語で会話をしていた影響が大きかったと思うのです。
我が家と反対に、お父さんの英語がマレー語訛り、マンダリン語訛りであっても、密着度の高いお母さんの母国語が英語である場合、ここマレーシアで同じ幼稚園に通っていても、そのミックスの子供たちの英会話能力は、幼い頃から高いのです。
我が家での英語力向上経過は、ここマレーシアの英語を話す地元の子供たちと同じような環境であったかもしれません。
いえ、実は、日本語訛りと生粋のイギリス英語にまじり、マレーシア訛り、オージー訛りにフランス訛りの英語がとびかう環境の中、0歳からマレーシアで育った息子が4歳になるまで言葉がでてこなかったように、地元のマレーシア訛りの英語とそれぞれの家庭での言語に慣れている子供たちのほうが、もっと単純な言語環境なのかもしれません。
また、どんなに日常会話ができても、イギリスカリキュラムで、文章の理解度、表現力をあげるには、普段からの文学小説の読み込み量に、それなりの勉強量が必要となってきます。
これは、日本語も同じく、英語を母国語とする全ての人たちの語学能力が高いかというと、そうではないのと同じです。
こういった背景もあるのだとおもいます。現地の子供たちの多いマンダリンが飛び交っているようなところでは、英文学等のクラスがなく、マンダリンであったりマレー語を第一言語とし、英語を第二言語(ESL)で、理数系を主に取り入れているところが多いのかもしれません。
スリアラでも、中学になってインター部門へ転入してくる生徒の中には、数学や英語力に応じて、1~2学年おとしたり、また、英語力が少しおとっていても、理数系能力が高い場合は、
IGCSEに向けて、
マンダリンを第一言語とし、
英語はESL、英文学や歴史等を選択せず、
理科の3教科に、
ビジネススタディや
会計学に
アートなどを選考する生徒たちもいます。(こういった選択は、Year 10、日本で言うと高1にあたる時点で決定します。)
こういった科目の必要なカレッジやカレッジ大学にいくのであれば、もちろん、こういった選択で全く問題がないのです。
このように、英語を第一言語としなくても、理数系に力をいれたり、また、会計学などを選考し、IGCSEコースで、ビジネス方面へすすむことができるのも、ケンブリッジカリキュラムのいいところでもあると思います。
我が子の場合、小学校5年生ごろまでは、感想文であったり、テストの解答文章を読んで、なんだか表現力に乏しいな、あれだけ本を読んでいるのに、読解力がないのだろうかと不思議でなりませんでした。
そんな中、返答が英語のみとなってきた日本語での話しかけをあきらめていた私本人が、子供の読んだ本について話す際、日本語で出来るほどの説明が、英語では流暢に表現出来ず、その都度、なんとも歯痒い思いをしていたこともあり、娘の表現力の幼稚さも仕方がないかと思っていました。
そんな幼稚園、小学校時、少し違うことをしていたかなと思うのは、子供たちの興味のある動物、物語や歴史などに関しての食卓でのゲーム、
テレビをみる代わりに、テレビの前で好きな本を声をだして読みきる、歌う、踊るなんてことです。
あとは、平日も週末も、プレイオーバー、スリープオーバーと、いつも友人たちと遊べる環境をつくっていました。
ほぼ、遊びが中心で、これといった対策もとらないまま、中学1、2年となる頃に、ようやく、その文章から、読解力に表現力がついてきているのが目に見えてあらわれてきました。
これは、もちろん、従来の読書量もさることながら、友人たちと楽しく遊ぶばかりでなく、喧嘩の場面もあったり、ずいぶんと悲しいおもいをした別れがあったり、正直言って、ふと私たちが育ってきたことのことを考えると、いやな思いをしたり、我慢をしたりと、物事の捉え方にも幅がでてきたのだろうな、と、非常に当たり前のことなのですが、改めて、
子供社会での遊びの重要さを考えさせられます。
もちろん、学校での授業に興味がわいてきて、もっと知りたいという勉強に対する意識があがってきたことも大きいのだと思います。
では、英語力と学力を伸ばすには、
どうすればいいのか
今回の両親面談で、学校での様子、成績表を受けとり、もしかしたら、点数と評価を気にされている家庭もあるかもしれません。
かくいう私も、娘の成績表の中、ガクンと落ち込んでいるビジネススタディの点数をみて愕然としながらの教科担当先生との対話では、IGCSEコースで、ビジネスをとらなければ全く問題のない教科だし、それに、本人がまったく興味がないといってるからね、とのこと。
授業態度が気になった私の質問には、眠っているかなと思うほど大人しくて迷惑かけてないから大丈夫、とのこと。これは、他教科担当先生達による娘の授業中の姿勢と比べると、どれだけやる気がないかというのがわかります。そして、もちろん教科担当先生にも、ひしひしと伝わっています。
実は、去年、あまり芳しくないビジネスのテスト結果を持ち帰った娘と、気がぬけるほどの数学テスト結果の息子の二人を前に、息子には、数学、苦手だからしょうがないけど、次はもうちょっとやってみる?でもさ、歴史は、よく学校で習ったことを話してるから、よくおぼえてるね、本当に興味があるんだね、と怒ることもなく意見を伝えた後、
娘には、出来のよい教科に関する評価はさておき、この質問みると、ビジネスは、授業きいてて、教科書おぼえたら、もう少し点数取れるんじゃないの、という冷たい評価のギャップに、非常に腹をたてていたなんて事件があったのです。
もちろん、今回の結果をみて、クラスでの態度をきいた際、去年の全く思いやりも戦略もない、私の気分次第の言葉が原因なのであろうことを痛感しながらも、また、改めて娘の意思の強さと頑固さを認識しながらも、先生に対し、いくら興味がないからって、もう少しできなきゃ変ですよね、なんて、他の子達は普通にできているのに、腹いせまぎれでしかない言葉をなげつけてしまいました。
反省。
もともと、ビジネススタディは、興味がわかないし、つまらない、なんていってたこともあり、本当は、興味がないわりには、そんなに悪くない点数だったね、なんていうべきだったんでしょうね。
本当に反省の日々ですが、私たちも親としては子供と同じ年齢。間違いを繰り返しながら一緒に成長しています。(すごいいいわけですね)
英語力(英会話ではなく勉学用英語力となる国語力)があがるまでには、1年どころか3~5年以上かかっても不思議ではないと、しっかりと親が自覚した上で、それぞれの子供の学習意欲がでてくるまでの時期もさまざまなため、決して他の子達とくらべたりしない事が大事だと思います。
目標は、他の子達に「まさる」ことではなく、本人の向上度です。
他と比べるのではなく、自身のテスト結果をみて、次回は5~10%は点数をあげたいな、といった直接的な目標をもって、学校の教科書とノートを、毎日繰り返し繰り返し、覚えるほど読みこんでいけるよう、はげましてください。
たとえば、中一ほどまでは、読み流すだけの15分~30分ほどのテスト勉強をしていた娘ですが、さすがに中2になってからは、テキストやノートを読み込んだ後、自分でまとめのノートをつくっています。
勉強の基本は、読んで理解し、それをまとめて書いてみる。
小学生高学年から口にしていた、「覚えるのに書かなくていいの?」を、言われたままにはやらなかったものの、授業できいて、テスト前に読み流すだけではおぼえきれない、と焦ったのか、中2の時点で、ようやくこんなまとめて書く習慣がでてきました。
とても地味で、大変ですが、これが、一番の学習法なのだと思います。
まずは、教科書などを暗記できるようになるまで読みこんでいく。
単語のひとつひとつの意味を日本語に訳し始めると、きりがありませんし、
英語を英語としておぼえていくことのほうが重要です。
電子辞書からはもう離れて、
紙をぺらぺらとめくれる英英辞書で語彙力をつけていきましょう。
また、基本的には、学校の授業と宿題のみで、塾等は必要ないと思うのですが、なんせ、英語を理解するためには、それぞれの教科での語彙数を増やすために時間をかけるしかありません。
これも、本人の意欲がでるまでは、どこまでやらせていいのかの判断が難しいのではないかと思うのです。
まずは、きちんとした英語をきいて、理解できるようになるまで協力していくしかありません。
勉強するしかないでしょ、というのは、私たち親のあせりです。
勉強するしかないんです。
でも、勉強するのって、とても大変なんです。
その大変さをわかるには、私たちも、いろいろなことを変えてみる必要もあります。
今回の懇談会、息子の件で、この年齢で、嫌いなことはやりたくないのは当たり前だから、家では、学校で学んだ中で気に入った話をするようにするだけでいいんじゃないのかな、クラスではとても意欲的に参加して、おもしろい意見をだしてくれるから、楽しいんだよね、といわれました。
そんな風にいつも心がけてはいるのです。
なのに、数学テストの結果をみて、4年後に受けるIGCSEを考え、親の私がひとりであせってしまう。
ちょうど、この懇談会の前日から、友人宅へおじゃましていた息子ですが、そこのお母さんとの会話で、ちゃんと勉強したら、あんなきれいなビルの最上階で仕事ができるからね、といわれ、僕、数学がぜんぜんできないから、その下のほうにいるんだろうね、と、すかさず返していたそうです。
本人が気にしてないんですもの、私が、4年先のことをあたふた心配しても、まだ、どうしようもありません。
また、悪い点数でも叱らない私の「あまやかし」を指摘されることもあります。
親の我慢力とのんきさも、大きな大きなキーだと思います。
いろんな失敗を重ねながら、なんとかなるさというのん気さと、やるしかないからねという勢いの使い分けでいきましょう。
私はずっとその繰り返しです。
以下のリンクは、英語のテスト対策の、エッセイ練習の特集です。
挑戦してみましょう。
いえいえ、お子さんではなく、あなたです。
Writing about a bar chart - http://goo.gl/CRpORj
Writing about survey results - http://goo.gl/uQZazY
An opinion essay - http://goo.gl/1S5re5
A for and against essay - http://goo.gl/07nwIV






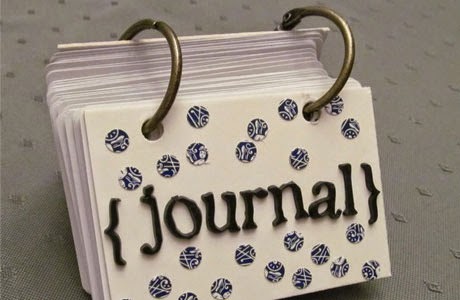





 特にブリティッシュ系のインターナショナルスクールでは、小学生高学年から、ドラマのクラスの中で、こういった古典を取り入れながら、英語文学や歴史になじんでいきます。
特にブリティッシュ系のインターナショナルスクールでは、小学生高学年から、ドラマのクラスの中で、こういった古典を取り入れながら、英語文学や歴史になじんでいきます。